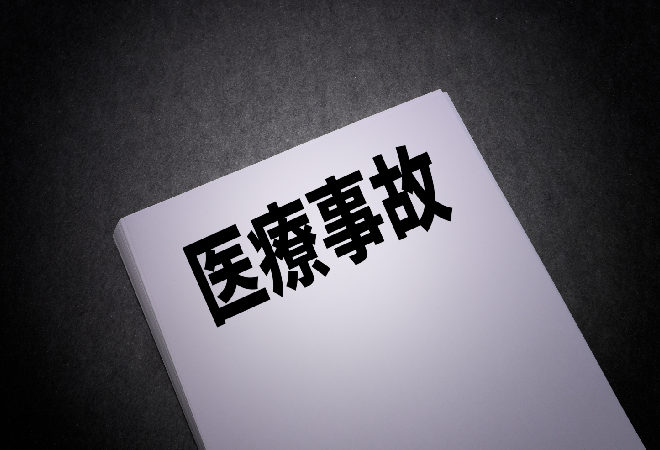
「手術は成功しました」そう言われて安心したのも束の間――術後の娘は目の動きが鈍く、言葉の反応も遅れているように見えた。「一時的なものです」と病院側は説明したが、父親としては明らかに“何かがおかしい”と感じていた。一週間たっても症状は変わらず、リハビリや診断結果の説明も曖昧なまま。「本当に医療ミスではないのか?」という不信感が拭えず、このままでは何も分からず終わってしまうのではという焦りも募る。この記事では、術後の異変に不安を抱えたご家族が、事実を確認するために取れる選択肢や、探偵の調査が有効に働く場面について解説します。
|
【この記事は下記の方に向けた内容です】
|
- 術後の様子が術前の説明と異なる
- 医師の説明が抽象的・あいまいである
- カルテや処置記録の開示を渋られてい
- 家族として何があったのか正確に知りたい
- 外部の第三者に中立的な調査をお願いした
術後の娘に異変…これは医療ミス?|50代男性からの調査相談
「回復は順調」と言われたのに…娘の様子がおかしい
相談者は都内に住む50代の男性。大学病院で行われた手術後、20代の娘の様子に不安を感じたといいます。医師からは「術後経過は良好」との説明を受けていましたが、退院後も娘は言葉の反応が遅く、視線が合わないことがありました。「何か変だ」と思って再診を求めても、「術後の一時的な影響だろう」とあっさり片づけられてしまい、納得できなかったといいます。カルテの開示も渋られ、家族に対する説明もどこか曖昧で、不信感が募っていったとのこと。「まさかとは思うが、もし医療ミスがあったのだとしたら、きちんと確認したい」と悩み、当会の無料相談窓口にご連絡いただきました。

術後に異変が出た患者家族が抱える問題点
術後の違和感を「家族の勘違い」と処理されてしまう背景
術後に現れる微細な異変や軽度の後遺症について、医療機関が真摯に説明しないケースが増えています。医療ミスという言葉には重い責任が伴うため、病院側が明確な説明を避けたり、家族の疑問を「神経質すぎる」「経過観察で様子を見る」と曖昧に処理する傾向があるのです。中には、記録の開示を拒否されたり、診療経過の情報が不自然に食い違うといったケースも報告されています。特に大学病院や大規模医療機関では、組織の保身が優先されることがあり、家族は「何が本当にあったのか」を知る手段を持てずに孤立してしまうことも。疑問を投げかけると医師や看護師の態度が急変するなど、不信感を募らせるきっかけも多く、説明責任を果たしてもらえないこと自体が新たな問題になり得るのです。
医療ミスのニュース記事(2025年7月時点)
- 医療ミスで新生児が仮死状態に 病院側「助産師2人が監視業務怠る」|参照:朝日新聞デジタル 2025年7月23日
- 宮城・石巻市立病院 医療ミスで70代男性死亡 1880万円余り損害賠償で合意|参照:東日本放送 2025年6月17日
問題を放置するリスク
病院側の説明に違和感を抱きつつも、「専門家の判断だから…」と受け身のままでいると、重大な事実がうやむやにされてしまう危険性があります。以下では、その主なリスクをご紹介します。
医療過誤があった場合でも、証拠が残らなければ事実の確認は極めて困難です。時間が経てば経つほど、記録の改ざんや隠蔽の可能性も否定できず、真相の解明が難しくなります。
病院側が「自然な経過」や「個体差」と説明すれば、それを否定する根拠がなければ家族の声はかき消されてしまいます。このままでは、再発防止もできず、同様の事例が繰り返される可能性も。
原因が不明のまま対症療法だけが続けられると、適切な治療やリハビリの選択を誤る可能性があります。本当の原因を知ることで、回復の可能性を高める手段が見つかるかもしれません。
法的な責任を問いたい場合、時効や立証責任のハードルが高くなります。確実な記録や証拠が早期に得られていないと、訴訟や示談を進めるにも不利になるリスクがあります。
説明が不十分なままでは、家族が「本当にこれでよかったのか」と悩み続けることになります。事実を知ることは、納得や前向きな気持ちを取り戻すうえでも必要なプロセスです。
医療ミスを疑ったとき家族ができる初期対応
術後の異変に気づいたとき、「まさか医療ミスでは?」と感じても、すぐに声を上げるのは勇気がいることです。しかし、病院側の説明に疑問が残るままにしておくと、時間の経過とともに真実の解明は難しくなってしまいます。ここでは、ご家族ができる現実的な備えや対応についてご紹介します。
家族ができる3つの初期対策
- 症状と経過を記録しておく:術後の様子に違和感を覚えたら、いつ・どこで・どんな異変があったのかを具体的に記録しましょう。音声や動画で残すのも有効です。診察時のメモや医師 の説明も日付入りで残しておくと、後々の証拠になります。
- カルテや診療記録の開示を求める:医療ミスが疑われる場合、カルテ・看護記録・麻酔記録などを入手することで手術や処置の流れを確認できます。開示請求には法的根拠があり、正当な方法で依頼すれば病院側も対応義務があります。
- 第三者の意見を求める準備をする:感情的にならず冷静に対応するためにも、別の医療機関でセカンドオピニオンを受けることを検討しましょう。また、法的や調査的な専門家に相談しておくと、証拠保全や対応の選択肢が広がります。
自己判断の落とし穴
「家族として見守るしかない」と考え、自力で何とかしようとする方も少なくありません。しかし、感情だけに頼って問い詰めたり、独自に調査を試みたりすることで病院側に警戒されてしまうケースもあります。情報の取り扱いや発言の記録も専門性が求められる場面が多く、一歩間違えれば“クレーマー扱い”されてしまう恐れもあるのです。また、証拠の保存や収集方法を誤ると、あとで取り返しがつかなくなる可能性も。「もっと早く専門家に相談しておけばよかった…」と後悔するケースも少なくありません。小さな違和感であっても、正確に状況を把握するためには、慎重かつ計画的な対応が求められます。
病院では教えてくれない事実を知るには探偵調査が有効
術後の異変に疑問を抱いても、医療機関から十分な説明を得られないまま話を終わらせられてしまうことがあります。「家族の思い違いです」「個人差の範囲です」と言われてしまえば、一般の方にはそれが妥当なのかどうか判断できません。しかし、もし本当に医療ミスや不適切な対応があった場合、それを知るには専門的な調査が必要です。探偵に依頼すれば、医療関係者の証言収集や記録の時系列確認、病院側の不審な動きの裏付けなど、病院外からの視点で客観的な情報収集が可能になります。問題を明らかにすることで、必要な交渉や対処に備えるための材料が手に入るのです。
探偵調査の有効性
「何が実際に行われていたのか」「どの段階で異変が起きたのか」を明らかにするには、院内での対応や処置の実態を客観的に確認することが重要です。探偵調査では、病院関係者の証言、当日のスタッフ配置や対応記録などの時系列情報を整理し、ミスや過失が疑われる対応がなかったかを外部から検証します。また、記録上は問題がないように見えても、実際の対応と矛盾しているケースもあり、その乖離を証拠として可視化することが、責任を問うための足がかりとなります。
病院に知られずに調査を進めることが可能です。医療ミスを疑っていることを表に出してしまうと、対応がより閉鎖的になったり、証拠が隠蔽されるおそれもあります。探偵は慎重に情報を集め、家族の立場を守りながら真相を追跡します。
集めた情報をもとに、弁護士と連携して対応を進めることができます。示談や訴訟のための準備を整えるほか、病院側に対して説明責任を求める際にも、第三者調査で得た客観的な証拠が有効です。
病院対応に不信を抱いたら、まずは専門家へ相談を
専門家へご相談ください
術後の異変に対し「このまま様子を見るしかない」と言われ、納得できないまま時間が過ぎてしまう――そんな状況に心をすり減らしていませんか?家族の違和感は、見過ごしてはいけない重要なサインかもしれません。「おかしい」と思ったときに何もしなければ、証拠も記録も失われてしまう可能性があります。医療機関を相手に事実を明らかにするには、高度な情報収集と専門的な対応が求められます。しかし、自分で動くと病院側に警戒され、説明や記録が改ざん・隠蔽されるリスクすらあるのです。探偵に依頼すれば、病院内部の動きや関係者の証言、記録との矛盾点などを、秘密裏に収集することが可能です。証拠が得られれば、弁護士と連携して病院に説明責任を求めたり、損害賠償請求を検討したりする上で有利に働きます。さらに、調査を通じて「本当にミスだったのか、それとも不可避の結果だったのか」を明らかにすることができ、心の整理にもつながるはずです。このまま「仕方なかった」と片づけてしまえば、真実は闇の中に埋もれてしまいます。小さな違和感でも放置せず、まずは専門家に相談してみてください。相談は無料です。家族の不安に寄り添い、事実を明らかにするための第一歩として、調査の力を活用する方が増えています。
※当サイトに掲載している事例・相談内容は、探偵業法第十条に基づき、プライバシー保護の観点から個人が特定されないよう一部編集・加工を行っています。トラブル探偵は、身近な生活トラブルに幅広く対応する調査サービスとして、ご相談者の安心と安全を最優先に考え、情報の取り扱いには十分な配慮を行っています。
週刊文春に掲載 2025年6月5日号
探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者
トラブル調査担当:北野
この記事は、皆様が抱えるトラブルや問題の悩みに寄り添い、解決への一歩を踏み出せるきっかけになればと作成しました。日々の生活の中で困っていることや、不安に感じていることがあれば、当相談室へお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、お力になれれば幸いです。

この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。日々生活をしている中でトラブルや問題ごとはご自身が引き起こさなくても起きてしまうこともあります。正しい知識と対処法は自身を守るためにも必要でしょう。時には専門家の手を借りることも必要になることがあるかもしれません。法的に守られるべき権利を持つ皆様が、安心して生活できるよう、法の専門家としてサポートいたします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
日常の中で起きるトラブルごとや問題は、お金や物だけではなく時に心身に大きな負担をもたらすこともあります。この記事を通じて、少しでも皆様の心の負担を軽くし、前向きな気持ちで生活を送っていただけるように、内容を監修しました。あなたの気持ちを理解し、寄り添うことを大切にしています。困ったことがあれば、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。心のケアも、私たちの大切な役割です。
24時間365日ご相談受付中

生活トラブル相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。
トラブル被害・トラブル調査の相談、解決サポートに関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)
トラブル被害・トラブル調査の相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。
トラブル被害・トラブル調査に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された被害相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。


